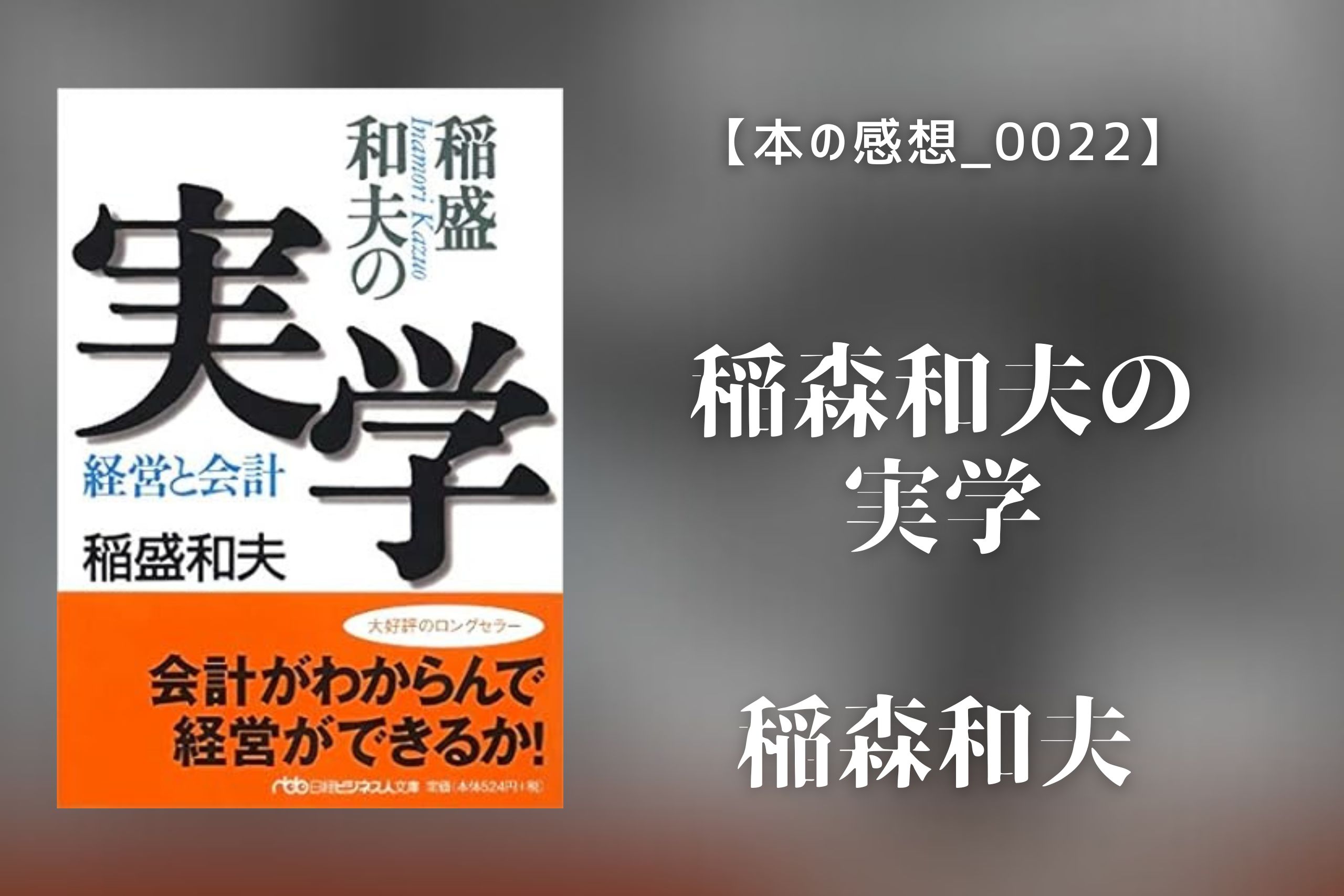
本のタイトル:稲森和夫の実学
著者の紹介:
稲森和夫
1932年鹿児島県生まれ。59年県京セラを設立。84年には第二電電(KDDI)を設立。2010年日本航空(JAL)会長に就任。若手経営者のための経営塾盛和塾の塾長として後進の育成にも神経を注ぐ。
Takeaways:
1. 経営に関する数字のあるべき姿
真剣に経営に取り組もうとするなら、経営に関する数字は全て、いかなる操作も加えられない経営の実態を表す唯一の真実を示すものでなければならない。損益計算書や貸借対照表のすべての科目とその細目の数字も、誰から見ても何一つ違いもない完璧なもの、会社の実態を100%表すものでなければならない。なぜなら、これらの数字は飛行機の操縦席にあるコップピットのメーターの数値に匹敵するものであり、経営者をして目標にまで正しく到達させるためのインジケーターの役割を果たさなくてはならないからである。
2. 人として何が正しいのかという事を判断のベースにする
ここでは、私の経営学、会計学の原点にある基本的な考え方について説明したい。それは、原理原則に則って、物事の本質を追求して、人間として何が正しいかで判断する。
物事の判断にあたっては、常にその本質に遡ること、そして人間としての基本的なモラル、良心に基づいて、何が正しいのかを基準として判断することが最も重要である。
27歳で初めて会社経営というものに直面して以来、現在に至るまで、私はこのような考え方で経営を行ってきた。私がいう人間として正しいこととは、例えば幼い頃、田舎の両親から「これはしてはならない。」「これはしてもいい。」と言われたことや、小学校や中学校の先生に教えられた「良いこと、悪いこと」というような、極めて素朴な倫理観に基づいたものである。
それは簡単に言えば、公平、公正、正義、努力、勇気、博愛、謙虚、誠実というような言葉で表現できるものである。経営の場において、私はいわゆる戦略・戦術を考える前に、このように人間として何が正しいのかということを判断のベースとしてまず考えるようにしている。
3. 減価償却と原理原則による判断
会計の分野における原理原則に則った判断というものについて、固定資産の減価償却に用いられる「耐用年数」の例で考えてみたい。
例えば経理の担当者に「機械を買うとなぜ減価償却が必要になるのか」と尋ねるとする。「機械というものは、使っても形を変えずに残っている。原材料のように使えば製品に姿を変えてなくなってしまうようなものとは違う。それゆえ、何年も動く機械を買ったのに、一時に全て費用として落としてしまうのはおかしい。かといって散々使ったあげく、捨てるときに初めて費用に落とすと言うのも明らかに不合理である。その機械がきちんと動き、製品を作ることができる耐用年数を定めて、その期間にわたって費用に計上するのが正しい。」という考えが返ってくるであろう。これは納得のいく話である。
ところが経理の常識では、その耐用年数について、いわゆる「法定耐用年数」に従って償却することを考える。大蔵省(現在の財務省)の省令の一覧表に当てはめて償却年数を決めるのである。
例えば、その一覧表によると、セラミックの粉末を成型する設備は「陶磁器・粘土製品・耐火物等の製造設備」の項目に該当し、耐用年数は12年されている。この規定に従えば、非常に固いセラミックの粉末を生成するため、摩耗が激しい機械設備でも12年で償却することになる。(※補足:法定耐用年数は12年でもはもっと早くダメになる。5~6年)
一方、摩耗がそれほど激しくない。菓子製造用の砂糖やメリケン粉をこねる機械は「パン、または菓子類、製造設備」の項目に該当し、耐用年数は9年とセラミックより短くなっている。これは容易に納得できることではない。(※補足:菓子製造設備がどれくらい持つのかは知らないが、恐らくセラミックよりは長く持つ。)
それぞれの機械が正常に機能する期間で費用に計上することが当然であるにもかかわらず、実際には法定耐用年数に無理矢理当てはめると言う決め方をされて、経営者として平然としていられるだろうか。
法定耐用年数というものは、「公平な課税」を重視する税法において定められたものであり、個々の企業の状況の相違を認めないで、一律公平に償却させるためのものである。
私の経験では、セラミックの粉を四六時中練れば、機械の保守をきちんとして、ちゃんと大切に使っていても、せいぜい5、6年持たせるのが精一杯である。そうであれば、償却も実際に機械を正常に使える年数で行うべきであろう。
しかし経理税務の専門家は、「決算処理上6年で償却したとしても、税法上は12年で償却しなければならない。だから、もしそうすれば最初の6年は償却が増え、利益は減る。ところが税金計算では法定耐用年数の12年での償却となるので、利益は減ってもその分の税金は減らないことになる。いわゆる税金を払って償却する有税償却になる」と言うであろう。
また、「税務上の耐用年数が法令で定められており、みんながこれに従っているのに、わざわざ無理に異なったことをやるのは懸命ではない。実務的にも償却計算が二本立てになって煩雑になる」と主張するかもしれない。
このような専門家の意見にたじろいで、多くの経営者は「そのようなものか」と思ってしまうのではないだろうか。
例えば実務上の常識がそうであったとしても、経営や会計の原理原則に従えば有税であっても償却すべきである。6年でダメになるものを12年で償却したら、使えなくなっても償却を続けることになる。
すなわち、実際に使っている6年間は償却が過少計上されており、その分が後の6年に先送りされていることになる。発生している費用を計上せず、当面の利益を増やすというのは、経営の原則にも、会計の原則にも反する。そんなことを毎年平然と続けているような会社に将来などあるはずがない。
法定耐用年数を使うという慣行に流され、償却とは一体何であり、それは経営的な判断としてどうあるべきなのか、という本質的な問題が忘れられられてしまっているのである。
だから、京セラにおいては法定耐用年数に使わずに、設備の物理的、経済的寿命から判断して、自主耐用年数を定めて償却を行うようにした。具体的には、製造設備の耐用年数は4年~6年とおおむね税法で定められた年数の半分としているが、変化が特に激しい通信機器関係の設備では、税法上10年なる法定耐用年数を大幅に短縮している。このように、会計的にはいわゆる有税償却を実施し、税務上では税法で定められた対応年数による償却計算を別途行っている。
4. 常識に支配されない判断基準
常識とされているものが、人の心をいかに強く支配するかと言うことを、私が若い頃実際に経験した例で話してみたい。………省略
いくら常識だと言っても、道理から見ておかしいと思った事は、必ず最後には「おかしい」と世間から認められるようになる。
売り上げに対する販管費・一般管理費の割合にも常識と呼ばれる迷信がある。例えばある業界で、販売費・一般管理費が売り上げの15%はかかるということが常識となっているとする。
販売組織や販売方法が各社みな類似していることが背景にあろう。そこで新しく参入してくる企業が、売り上げに対して販売費一般管理費が15%かかると言う常識を前提にして経営をすると、意図せず自然のうちに同業他社と横並びの経営になってしまう。
これでは「自社の製品をより効率的に販売するためには、一体どのような販売組織や販売方法取るべきなのか」という、重要な経営課題を根本的に考える機会を自ら放棄し、他社模倣することになる。
それだけではない。例えば、この業種でこの規模なら売上高利益率は、税引き後で5~6%であるという常識にとらわれてしまえば、どうしても結果として、利益はその水準にとどまる。不思議なことに、前年賃金が上昇しても、その水準の利益は出せるが、それ以上の利益がどうしても出せなくなるのである。
これらの例は、いわゆる常識というものに、不思議なほど簡単にとらわれてしまうものかをよく示していると、もちろん私は常識とされていることを、とにかく頭から否定すべきと言っているのではない。問題は、本来限定的にしか当てはまらない常識を、まるで常に成立するものと勘違いし、鵜呑みにしてしまうことである。このような常識にとらわれず、本質を見極め、正しい判断の積み重ねていくことが絶えず変化する経営環境の中では必要なのである。
5. 売上を最大に、経費を最小に
経営者は誰でも利益を追求するのだが、多くの経営者が売上を増加させようとすると、当然経費も増えるものと思っている。これがいる経営の常識なのである。
しかし「売上を最大に、経費を最小に」ということを経営の原点とするならば、売上を増やしていきながら経費を増やすのではなく、経費は同じか、できれば減少させるべきだと言うことになる。そういう経営が最も道理にかなっていることに、その時私は初めて気づいたのである。
売上を増やしながら経費を減らすと言うのは、生半可のことで達成できることではない。そのためには知恵と創意工夫と努力が必要になる。利益とはその結果生まれてくるものでしかないのである。
6. 値決めは経営
事業においてその収益源である売上を最大に伸ばしていくためには、値段の付け方が決め手となる。値決めは、単に売るため、注文を取るためという営業だけの問題ではなく、経営の死命を決する問題である。
売り手にも買い手にも満足を与える値なければならず、最終的には経営者が判断するべき大変重要な仕事なのである。
京セラは創業当時から電子機器メーカーに電子部品を収めてきたが、電子部品の業界は新規参入も多く、競争が激しいため、当時無名に近かった京セラに対して、いつも非常に厳しい値下げの要求があった。競合品があれば天秤にかけられて、徹底的に値切られた、また毎年毎年値段を下げられた。
そうなってくると営業は注文を取るためにいくらでも値段を下げていく。こんなことをしていたらどうにもならないので、私は「商売というのは、値段を安くすれば誰でも売れる。それでは経営は出来ない。お客様が納得し、喜んで買ってくれる最大限の値段。それよりも低かったら簡単に注文は取れるが、それ以上高ければ注文が逃げるという、このギリギリの一点の値段で注文を取るようにしなければならない」ということを、社内の営業部門に対して繰り返し強調した。
顧客が喜んで買ってくれる最高の値段を見抜いて、その値段で売る。その値決めは経営と直接する重要な仕事であり、それを決定するのは経営者の仕事なのである。
つまり売上を最大にするには、単価と販売量の積を最大とすれば良い。利幅を多めにして少なく売って商売をするのか、利幅を抑えて大量に売って商売をするのか、値決めで経営は大きく変わる。
7. うどんの屋台
売値の決め方に知恵を絞り、経費を最小とするように努力をしていく例として、私は会社の幹部にしばしば「うどんの屋台を出す」という話をした。経営者を育てるためには極論ではあるが、うどんの屋台を引っ張らせて、街角でうどんを売らせるという方法が効果的な実習となるだろうと考えたからである。
5万円の元手を出して、「しばらく会社に出て来なくてもよろしい。屋台一式貸すから、1ヵ月間毎晩京都のどこかでうどんを売ること。この5万円を1ヵ月後いくらにして持って帰ってくるのかが実績だ」と、実地訓練に送り出す。
まず1番に来るのは仕入れの問題である。最初にうどん玉を買わなければならない。製麺所まで買いに行くという方法もあれば、スーパーで売っている生麺を買ってくる方法もある。硬い干し麺を買ってきて、茹でてで出すことも考えられる。
次は出汁である。良い味を出すためには出汁がポイントとなる。高い鰹節を買ってくる者もいれば、鰹節を削っているところで屑になった鰹節をもらってくるものもいるだろう。同じうまい出汁を出すにしても、工夫によって全然違う。原価を安くしていかに良い味を出すのかの創意工夫が必要である。
そして肝心なのが売値である。1杯300円のうどんもあれば、500円のものもある。安ければいくらでも売れるだろうが、利益を得ることができない。お客さんを満足させて売れるベストの値段を探し出さなくてはならない。
このようにうどんの屋台1つでもいろんな選択肢がある。一晩に出てくる差はわずかでも、年間にすればものすごい差になってくる。だから、屋台から大きなフランチャイズチェーンに発展させる人もいるし、何十年台を引いても何も財産を残せない人もいる。
良い商売、悪い商売があるのではなく、それを成功に導けるかどうかなのである。売上を最大にするように、正しい値決めができれば、後は「経費を最小に」を徹底して行っていけばいい。
8. 会計がわからなければ、真の経営者になれない
我々を取り巻く世界は、一見複雑に見えるが、本来原理原則に基づいた「シンプル」なものが投影されて、複雑に映し出されているものでしかない。これは企業経営でも同じである。
会計の分野では、複雑そうに見える会社経営の実態を,、数字によって極めて単純に表現することによって、その本当の姿を映し出そうとしている。
もし経営を飛行機の操縦に例えるなら、会計データは経営のコックピットにある計器盤に現れる数字に相当する。
計器は経営者たる機長に、刻々と変わる機体の高度、速度、姿勢、方向を正確にかつ即時に示すことができなければならない。そのような計器盤がなければ、今どこを飛んでいるのか分からないわけだから、まともな操縦などをできるはずがない。
だから、会計というものは、経営の結果を後から追いかけるためだけのものであってはならない。いかに正確な決算処理がなされてたとしても、遅すぎては何の手も打てなくなる。
会計データは、現在の経営状態をシンプルに、またリアルタイムで伝えるものでなければ、経営者にとっては何の意味もないのである。
その証拠に急速に発展している中小企業が、突然経営破綻を起こすことがある。会社の実態を即座に明確に伝える会計システムが整備されておらず、ドンブリ勘定となっているため、経営判断を誤り、最終的に資金繰りに行き詰まってしまうのである。
中小企業が健全に成長していくためには、経営の状態を一目瞭然に示し、かつ経営者の意思を徹底できる会計システムを構築しなくてはならない。
京セラが継続な事業展開ができたのは、そのような会計システムを早いうちから整備し、それによって経営を進めることができたからである。
そのためには、まず経営者が会計というものをよく理解しなければならない。計器盤に表示されている数字の意味するところを。手に取るように理解できるようにならなければ本当の経営者とは言えない。
経理が準備する決算書を見て、例えばの伸び悩む収益のうめき声や、痩せた自己資本が泣いている声を聞き取れる経営者にならなければならないのである。
9. 資産か、費用か
例えば、あるものを資産として残すのか、費用として落とすのか、経営上これによって大きな違いが出てくる。
かつて私は経理部長に次のような話をした事がある。極端な話だが、例えば街でバナナの叩き売りをやるとする。まず青果市場でバナナを1箱仕入れる。駅前で叩き売りをしようと手近の八百屋に行って、りんご箱を1つ分けてくれと言い、空いたりんご箱を300円で買う。りんご箱の上にかける大きな布もいるので、隣の雑貨屋で1枚1000円買う。棒がないと叩き売りにならないので、200円で仕入れる。こうして商売の道具を一式揃える。バナナは1房50円で20房仕入れた。バナナの仕入合計は1000円。それを150円で売ることにする。1房売れば100円儲かるわけだ。
そこで日が暮れるまでに幸い全部売れたとしよう。1房150円のバナナが20個全て売れたので売上が3000円、仕入れた原価は1000円だから、儲けは2000円という事だが、勘定してみるとお金はそんなにはない。その理由は、りんご箱に300円、布に1000円、棒で200円と、道具に1500円払ってるので、手元には500円しか残らないわけだ。
仮にそこへ税務署が来て、あなたは売上2000円だから、その半分の1000円を税金として払えと言うとする。手持ちは500円しかないのになぜ1000円も税金を払うことになるのかと問うと、りんご箱と布と棒は費用ではなく資産だと言う。1500円資産と500円の手残りで合計2000円なり、それに税金がかかると言うのである。
税務署はりんご箱が立派な資産だと言うが、明日には次の土地に移るので捨てていかなければならない。りんご箱を分けてもらった八百屋に行って買い戻してほしいと言っても、「タダならもらってやるよ」と言われるのがオチである。布だって下ろしたてのパリッとしたものであってこそ、バナナが美味しそうに見え、売れるのだ。結局りんご箱も布も棒も資産としての価値は無い。
何度も繰り返し使えて、その価値が残るものは会計上資産とすることになっているが、本当に財産としての価値を持つものなのか、そうでないのかというのは経営者が判断すべきものである。そしてその判断の良し悪しの結果は、すべて経営者の責任である。
経営者にとって、捨てる以外に他がないものは資産とは言えず、経費で落とすべきである。りんご箱は3000円売り上げるために使った経費であって、八百屋でまたお金を払って買い戻ししてくれるような資産では無いからだ。
この話は、あるものを費用にするか、資産にするかということによって、会計的には大きな違いになることを単純化した例えで示したものである。実際にはもちろん固定資産は土地などを除いて減価償却ができるし、小額のものであれば一時に経費に落とすことが税法でも認められている。いずれにしてもバナナを売るために買った道具が使い捨てのものなら、それはすべて経費なのである。
3000円の収入を得るために合計1500日の経費を払ったから、売上3000円-仕入1000円-経費1500円で最終的な手残りは500円。それが手元に資金として存在するわけである。この手残りに税金を払った後は自由に使える。
しかし1500円で買った道具は資産だから、売上3000-仕入1000で儲けは合計2000円だと思い込み、実質の手残りの500円以上使ってしまえば、たちまち資金繰りが行き詰まってしまう。だから、支出されたものは、資産として抱え込まずに、できるだけ早く費用として処理しなければならない。
10. 土俵の真ん中で相撲を取る
お金のことを常に心配していては仕事ができない。そのためギリギリの資金繰りは決してしないようにしなければならない。
手形が落ちないと言って必死に金策に走り、ようやく手形を落とし、あたかもすごい経営努力をしているかのように思い込んでいる人がいる。
しかし常に金作に走り回って自転車操業しているようでは、本当の経営を行っているとは言えない。マイナスの経営をやっとのことでプラマイゼロの水準に戻しただけのことである。
京セラを創業して間もない頃、私は松下幸之助氏の講演を聞く機会があった。その講演のテーマは「ダム式経営」というものであった。
幸之助氏は会社を経営する際、ダムを作ることで、川がいつも一定の水量で流れているように、ダムの蓄えを持って事業を進めていかなければならないと説かれた。話の後、質疑応答の際に聴衆の1人が、「どうやったらそのような余裕のある経営ができるのでしょうか」と尋ねた。幸之助氏は「その答えは自分も知りません。しかしそのような余裕のある経営が必要だと思わないといなけいですな」と答えた。
聴衆の多くはこの答えに笑ったが、私はこの言葉に深く心を動かされた。何かを成そうとするときは、まず心の底からそうしたいと思い込まなければならない。分かってはいるけれど、現実にそんな事は不可能だと少しでも思ってしまったら、どんなことも実現することができない。どうしてもこうでなければならない、こうしたいという強い意思が、経営者には必要なのである。
11. 京セラの自己資本比率
私がとにかく借金はできるだけ早く返そうとしたため、比較的早い時期から京セラは自己資本の比率を高くすることができた。具体的には上のグラフの通り創業より15年目で総資産に占める自己資本の比率を70%近くまで高めることができた。
12. 一対一対応の原則
経営活動においては、必ずモノとお金が動く。その時はモノまたはお金と、伝票が必ず一対1の対応を保たなければならない。この原則を「一対一対応の原則」と私は呼んでいる。
これは一見当たり前であるが、実際には様々な理由で守られていないのが現実である。
例えば伝票だけが先に処理されて、品物は後で届けられる。これと逆に、ものはとりあえず届けられたが、伝票は翌日発行されるといったことが、一流企業と言われる会社でも頻繁に行われている。
このような「伝票操作」ないし、「簿外処理」が少しでも許されるということは、数字が便法によっていくらでも変えられるということを意味しており、極端に言えば企業の決算などは信用するに値しないと言うことになる。
実際期末に苦し紛れに売上を水増しする例もよくあると聞く。取引先に電話を入れて「今期売り上げがどうしても足りない。これこれの内容で10億円の売上伝票をこちらで立てるが、来期早々に返品を入れて元に戻すので、よろしく。」というような依頼をする。取引先との辻褄だけ合わせて伝票を上げて、期末の売上を少しでもよく見せようというのである。
このようなことが1度でもあると、社員の感覚が麻痺してしまい、数字は操作できるもの、操作して当然のものと考えるようになってしまう。その結果、社内の管理は形だけのものとなり、組織のモラルを大きく低下させる。数字はごまかせば良いということになったら、社員は誰も真面目に働かなくなる。そんな会社が発展していくはずがない。
13. 顧客満足と経理処理を正確に行う事は全く別
「一対一の対応」は、企業の中であらゆる瞬間に成立していなければならない。
客先に製品を出荷するときは、必ず出荷伝票を発行して売上を計上し、以後売掛金として管理し、入金までフォローする。製品の配送を運送業者に託しても、あるいは営業マンが客先に直接届けに行く場合でもこの手続きは同じである。
京セラの創業当初は、納入する客先の多くは、企業の研究所や公的な研究機関であった。その研究者から「こういう実験をやりたいので、こういうものをセラミックで作ってほしい」と頼まれて、様々な製品を作っていた。先方の実験の進み具合によって、約束した納期などはさておき、「とにかくできた分だけでもすぐに持ってくるように。」と急に言われることも珍しくなかった。
そのような時は営業が慌てて飛んでいき、ともかく品物だけを置いて帰ってくると言うこともあった。製品を動かす場合には必ず伝票を一対一の対応で発行する必要があるのに、「大至急必要となった。夜中になってもいいから何とか届けてくれ。」と言われて、まだ製造の現場にあるものをとりあえずあるだけ届ける。夜中であるから正規の事務処理ができない。「伝票は明日に。」と思いつつ、いつの間にか忙しさに紛れて忘れてしまう。月末近くになって製造の方から「あれはどうした?いつ売り上げになるのか。」と言われて、慌てて飛んでいっても、先方では頭の製品はどこかに紛れ込んでしまって確認のしようがない。結局、伝票処理はされないまま、お金がもらえない。そのようなケースが数多くあった。
このような事は、客先を大切にしている会社ならいつでも起こりそうなことだが、私は顧客を満足させることと、経理処理を正確に行う事は全く別であり、両方とも徹底しなければならないと考えていた。だから、どんな場合でも一対一で伝票を発行しなければ、物を動かせないようなシステムを構築していたのである。
モノの動き、お金の動きを伴う事実が、全て一対一で伝票に起こされ、正規ルートで正しく処理されているという事は、非常に単純なように見えるが、それが健全な経営を守るためにどれほど大切なことであるかは、昨今の企業における不正処理、不祥事の数々を思い起こせば、容易にご理解いただけると思う。
14. 筋肉質の経営に徹する
企業は永遠に発展し続けなければならない。そのためには、企業を人間の体に例えるなら、体の隅々にまで血が通い、常に活性化されている引き締まった肉体を持つものにしなければならない。つまり経営者は、贅肉の全くない筋肉質の企業を目指すべきなのである。私はそのことを「筋肉質の経営に徹する」と表現しているが、それは私の会計学のバックボーンにもなっている。
例えば会社の株式が上場されると、どうしても会社をよく見られたいと言う意識が出てくる。高い株価を維持したいと言う欲求に駆られて、利益を始め、すべてのものをよく見せたいと思うようになるのである。しかし、見栄を張れば贅肉ばかりがつき、不要な負担を増やすばかりとなる。
誰でも人間は、少しでも自分をよく見せたいと言う気持ちがある。もしこのような虚栄心が強い経営者であれば、その企業は見せかけに飾られた贅肉だらけのものになるだろう。
本質的に強い企業にしようというのであれば、経営者が自分や企業を実力以上によく見せようと言う誘惑に打ち克つ、強い意思を持たなければならない。
15. 中古で済ませる
京セラも初期の頃は会社としての余裕もなく、とにかく倹約を旨としていた。事務所の机や椅子も新しいものを買うのではなく、中古屋の安いスチール家具を買ってきて使っていた。たとえ新入社員に対しても、事務作業をするのに新しい事務机や椅子がいるわけでは無いであろうと、中古の机を買って与えていた。
製造設備を購入する場合も、どうしても現場の技術者は新品の機械を買いたがるが、私は「機械や設備はもし中古で間に合うならそれで我慢せよ」と言ってきた。性能が優れた機械であっても容易に買う事は許さず、現在にある機械をいかに使いこなすかを徹底的に考え、創意工夫を凝らすよう教育してきた。
創業もない頃、初めて米国を訪問した際、競合するアメリカのセラミックメーカーの工場を見学する機械があった。そこには最新のドイツ製の素晴らしい機械が整然と並び、リズミカルに動いていた。京セラでは、自ら設計した機械を懸命に動かして苦労していた頃である。
最新鋭の工場を見て回りながら、ドイツ製の機械はスピードといい、性能といい、素晴らしいのに驚き、「この機械は1台いくらするんですか。」と尋ねると、そこの工場長が目の飛び出るような値段を答えた。その時すぐに私はこう考えた。「こんなに高価な機械だが、1分で一体何個作っているのだろう。京セラで使っている自作の機械でもこの半分は生産している。つまり生産性は半分という事になる。この設備投資の総額に比べて、その何十分の一の値段の機械の生産性が半分であるなら、設備投資の効率から言えば、我々の自作の機械の方が勝っているのではないか。」
普通はあまりそういう計算をせず、最新鋭の機械がなめらかに動いているのを見て、これに追いつかねばならないと、1日も早くその機械を導入することを考えるのではないだろうか。そのような設備投資を行えば生産性自体は必ず向上するであろうし、最新の技術を使っていると言う満足は得られるかもしれない。しかし実際は、それがそのまま経営効率の向上につながるとは限らないのである。
こういった見栄を張った過剰な設備投資を繰り返していく事は、かえって経営体質を弱めることになるし、限られた経営資源を大事に活かすということにもならないのである。
16. 利益と税金に影響を与える棚卸の考え方
メーカーの在庫販売や一般の流通業の場合でも、どうしても仕入れた中には売れ残るものが多かれ少なかれ出てくる。このようなものを含めて、在庫は仕入れた値段で棚卸しされているのが普通である。
また実際の棚卸しは、経営者が自ら行っているのではなく、担当者がモノの有る無しだけで通常実施している。そうしていると必ず長期間にわたり全く売れていない品物が、今後も売れる見込みもないのに、そこでホコリをかぶり、何度も棚卸しされているケースが出てくる。すなわちすでに価値のないものが財産として置いてあり、資産として計上されているのである。
こうして結果的に見せかけの利益だけが増えて、不必要な税金を払っているという場合が出てくるのである。その意味で棚卸しは人任せにせず、本来経営者が自分の目で見て、自分の手で触れて行うべきものである。
自分も一緒になって倉庫で検品をして、「これは3年前から一向に売れていないのではないか。これはもう捨てなさい。」と言って、こまめに見て回るようにすべきものである。
17. 固定費の増加は経営体質を弱くすることがある
設備投資は減価償却費として固定費の増加をもたらす。また人件費も固定費の中で大きな部分を占めており、正社員が増えればそれだけ固定費も増加するのである。特に間接部門(バックオフィス)では、いつの間にか人が増えているということになりやすい。
そこで筋肉質の経営をするために重要な事は、原材料等の操業の度に連動する変動費を下げるだけでなく、固定費を一定もしくはできるだけ下げて利益率を高めるということである。すなわち固定費用をできるだけ下げていくことで、損益分岐点を下げていき、結果として利益を増やしていくことである。
先ほど述べたドイツ製の高価な機械の例であれば、当時の自社製の機械は、その何十分の一と言う値段であり、固定費は非常に少なくて済む。またその頃は人件費の水準もドイツより日本の方が低かったため、設備の生産性がたとえ半分であっても、充分に対抗できるというわけである。
エンジニアや経営者も、優秀な最新鋭の機械を欲しがり、それを買わなければ、競争に負けると思い込みやすいが、逆に設備投入により固定費を大きく押し上げて、経営体質を弱くするということがあると言うことを十分に認識しておかなければならない。
18. 投機的利益を追わず、原理原則や行動の規範に従う
私にとって投資とは「自らの額に汗して働いて、利益を得るために必要な資金を投下すること」であって、苦労せずに利益を手に収めようとすることではない。
私の会計学には投機的利益を狙うという発想は微塵もない。だから余剰資金の運用については、元本保証の運用が大原則であり、その中に投機的な資金運用のための「リスク管理」等は全く含まれていない。
かつて「財テク」という言葉が当たり前のように使われ、企業の経理、財務部門でも一時的な運用利益を追った挙句に、最終的には会社の根幹を揺るがすほどの甚大な被害をもたらすという例が多く見られた。このようなことが起きるのは、自ら働いて得る利益を尊ぶという、原理原則を経営者が無視した結果である。
1973年10月に始まる第一次石油ショックによる日本経済の混乱がまだ続いている頃、ある都市銀行の支店長が訪ねてきてこう言われたことを覚えている。「2年位前から不動産が値上がりしています。皆さん土地を買って転売して儲けておられます。御社は利益が上がった分、当行に預金していただいて、それはそれでありがたいのですが、世間では金を借りてでも土地を買っておられます。今は手持ちの資金に、さらに銀行から借りて上乗せをして土地を買う時代です。御社には当行はいくらでもお貸しします。値上がり確実な不動産もたくさんありますので、ぜひ紹介させていただきたいのですが。」私は「自分で額に汗して稼いだものしか利益ではないと思っている」と述べて、この話を聞くだけで済ませた。
その半年か1年後に当時のバブルがはじけて、名の通った会社が次々に経営破綻に追い込まれた。その頃京セラはまだ小さな会社だったが、いくつかの雑誌や新聞の記者が訪ねてきてこう聞かれた。「今回の倒産劇を見てどう思われますか?どの企業も値下がりした不動産を抱え込んで困っていますが、京セラさんにはそういったことが一切なかったと聞いています。その先見性はどこから出てくるんですか?」私は率直に答えた。「皆さんが言われるような先見性があったのではないんです。ただ私は浮利を負うのが好きではありません。それだけのことです。不動産を転がすような金儲けは嫌だったということだけのことです。」
その後、1990年代初頭のバブル崩壊までに幾度かバブルが膨らんでは弾けている。1度火傷しても、時間が過ぎてしまうと、たちまちにその痛さを忘れ、同じことを繰り返しているのはなぜだろうか。
株や土地がいつまでも上がり続けるとは到底思えないのに、自分だけは損しないと信じ込んでしまう。
世の中の動きに駆り立てられると、それに逆らって自分の意思を貫くということは難しいことなのかもしれない。しかし、多くの社員に対して責任を負う経営者は、他人を見てその真似をするのではなく、あくまでも自分の中にある原理原則や行動の規範に従うべきである。時勢に付和雷同して流されるような経営をしてはならない。
19. 従来の予算制度 = 予算だけは厳守され、売上は計画通りにはいかない
通常来年度の事業計画を立てる場合、「売上は前期売上の何%増にしよう。それには当然マンパワーもいるだろうから、人員はこれだけ増やそう。さらにこれだけの売上を上げるためには、新たな支店を設けよう。そのための営業経費も増えるだろうから…」というように、必要な経費項目を全て上げて予算を作る。私は今までこのような予算制度を実施してこなかった。なぜなら、人を増やそう、支店を増やそうという、経費に関するものは計画通りにどんどん進んでいくが、肝心の売上が計画通りに増えないことが多いからである。
「売上はなぜ増えないのか」と尋ねると、「いや、頑張っているんですが、今は不況でなかなかうまくいきません。」というような答えが返ってくる。その上、「現状を挽回するためには、さらに思い切って人員を増やす必要があります。」というように、経費のみがさらに増えていく場合が多い。
もともと計画した売上を達成するため経費を使っているのだから、売上も経費に伴い増えていくべきなのだが、実際にはそうはならず費用だけが増えていく。つまり、使う方の予算だけは厳守され、入ってくる方の売上は期待通りに増えない。それが予算制度の実態ではないだろうか。
それゆえに私は、「予算制度はいらない。お金はその都度、稟議を出せ。その都度決済をする。」という方法で経営をしてきた。さらに京セラでは、原材料等の購買について毎月必要なものは毎月必要な分だけ購入するようにしている。場合によっては毎月ではなくて、毎日必要な分だけを買うようにしているケースもある。私はこれを「一升買い」と呼び、資材購入の原則としてきた。たとえ「一斗樽」でまとめて買えば安くなりますと言われても、今必要な一升だけを買うようにしてきたのである。
20. 当座買いの原則
このような子供の時の経験から、まとめて買えば安く上がったように思うけれども、実はそうではないと言うことを学んだ。
人間というのは面白いもので、5升買えば安くしますと言われればついつい買ってしまって、余分に使ってみたり、乱暴に使ってこぼしてしまったりするものなのである。
しかし今使う分しか手元になければそれを大事に使うようになる。だから一升いるなら一升しか買ってはならない。このようにして「当座買い」の重要性を学んだ。
私は京セラ創業後も経理部長に「一升買い論」としてよく説いていた。しかし経理部長のほうは、「そんな事は経営学でも経理の考え方でも常識に逆行することです。世の中のどんな経営学や会計学の本を見ても、安いものを買いなさいということはあっても、高いものも買いなさいということは言っていません」と言い張った。私は「そんな常識はどうでもよろしい。とにかくいる分だけ買いなさい。」と言って頑張ったことを覚えている。
そうやって反発していた。経理部長がしぶしぶ言われた通りにやっているうちに。「なるほど」と気づき始めたという。使う分だけ「当座買い」するから、高く買ったように見えるが、社員はあるものを大切に使うようになる。余分にないから倉庫もいらない。倉庫がいらないから、在庫管理もいらないし、在庫金利もかからない。これらのコストを通算すれば、その方がはるかに経済的である。セラミックのように腐らないものなら、まだしも、腐るものを扱う場合には、気がついてみたら使えなくなっていたということになりかねない。そのことが分かってきたのである。
経理部長は私に、「社長の子供の頃の話を笑い話みたいに聞いていましたけれども、素朴な話の中に含まれる真理が本当は大切なことであると気づきました。」と言うようになった。これを「当座買いの原則」または「一升買いの原則」と京セラでは呼び、現在も経営の鉄則として受け継がれている。
21. 創業者と2代目の違い。マクロとミクロの理解
完璧主義を貫くということは、曖昧さや妥協を許すことなく、あらゆる仕事を細部にわたって完璧に仕上げることを目指すものであり、経営においてとるべき「基本的な態度」である。
リーダーたるものは常にパーフェクトな決断を求められる。例えば登山隊のリーダーは判断を1つ間違えるとパーティー全体が死に直面することになる。同様に会社を経営する。社長もその判断が会社の運命を左右する。社長は従業員とその家族、顧客、株主協力、会社等に対し重大な責任を負っているのである。
その重大な責務果たすために経営者たるものは、会社全体のマクロな仕事と同時に、部下のやっているミクロの仕事も十分に分かっていなければ、完璧な仕事はできない。部下が休んだ時でも自ら変わって仕事ができる位でなければ、本当のリーダーとしての資格さえないと言える。
通常創業者の社長は現場の細かいことから会社全体の事までよく分かっている。ところが、創業者の後を継いだ2代目社長、専務といった後継者たちは、現場のことをあまり知らないケースが多い。お父さん、おじいさんから、リーダーとして全体をまとめていくマクロの帝王学は教わっていても、ミクロの現場の事はわかっていない。そのため、経営者として本当の意味で会社を動かせないのである。
もし企業のトップとして、本当に自分の思う通りに経営をしていこうとするのなら、足繁く現場に出て、現場の雰囲気、現場のことを知らなければならない。そこからでなければ帝王学も生きては来ない。マクロだけでなく、ミクロもわかっていなければ、経営者は自由自在に会社を経営することができないのである。
22. 完璧主義を目指す。その姿勢があるからミスが起こりにくくなる。
私が専攻した科学の世界では、多くの薬品を配合して新しい化学物質を作る。その時、薬品の配合をちょっと間違っただけでも、何日もかけて一生懸命やってきたことが全部ダメになってしまう。もし1年間かかって研究してきたものであれば、その1年間の努力が一瞬にしてムダになるのである。
また現代の製造業では「不良がゼロ」というのが当たり前というほど、品質に対する要求は厳しい。それは、すべてのプロセスにおいて完璧な仕事ができていない限り実現できない品質レベルである。このように研究機関や製造ではわずかなミス許されず、常に完璧な仕事が求められるのである。
ところが経理などの事務職では、間違えば「すいません。直します」で済んでしまう。私はよく経理部長に「事務屋はそれだからいかん」と言って怒った。ミスを犯しても、消しゴムで直せると思っていては、完璧な仕事は決してできない。少々の間違いくらいは仕方がないと思う人もいるかもしれない。しかし、投資計画にしろ、採算管理にしろ、基礎となる数字に少しでも誤りがあれば、結局経営判断を間違ってしまう。だから、研究開発や製造部門だけでなく、事務部門においても、真剣に経営をしようとすれば、ミスは全く許されるべきではない。
完璧主義を全うするのは難しいことだが、その完璧主義を守ろうとする姿勢があるから、ミスが起こりにくくなる。パーフェクトを目指してもミスがゼロになるわけでは無いかもしれない。しかしだからといって99%で良いだろうということにはならない。99%でも良いだとなれば、今度は90%でも仕方がないということになる。いや80%でもいいじゃないか、70%でも良いじゃないかとなるだろう。そうすると会社の経営は甘くなっていき、どんどん社内の規律も緩んでいくであろう。
100%は100%なのである。私は売上や利益の計画に対しても、「100%に達しなかったが、95%は達成できたので今回は許してください」と言う考え方は認めていない。製造や営業の経営目標に対する実績についても、開発スケジュールは管理の仕事の正確さについても、完璧な実行を要求している。
23. 最終的には心
中国の古典に、「天の時、地の利、人の和」という言葉がありますが、天の時や地の利を得たとしても、最終的に事を決するのは心のあり方なのです。




